食中毒は、じめじめとした梅雨や、暑い夏の時期に発生するイメージですが、、、
実は冬にも多いんです!!
冬に気をつけたいウイルス=ノロウイルス
冬場に増加する食中毒の代表といえば、「ノロウイルス」ですよね。
ウイルス性の食中毒は、低温や乾燥した場所で長く生きることができるため、冬場に増加します。
また、ノロウイルスは感染力がとても強く、感染規模が拡大することも多いため、発生件数も増加します。
- 時期 ・・・ 11月から2月にかけて
- 特徴 ・・・ 小さな球形、非常に強い感染力
- 経路 ・・・ ノロウイルスが付着した手で食事をしたり、
ノロウイルスが付着した食品を食べたりするなど
(汚染された二枚貝や井戸水などには特に気をつけましょう) - 潜伏期間 ・・・ 24時間~48時間
- 主な症状 ・・・ 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、37℃~38℃の発熱など
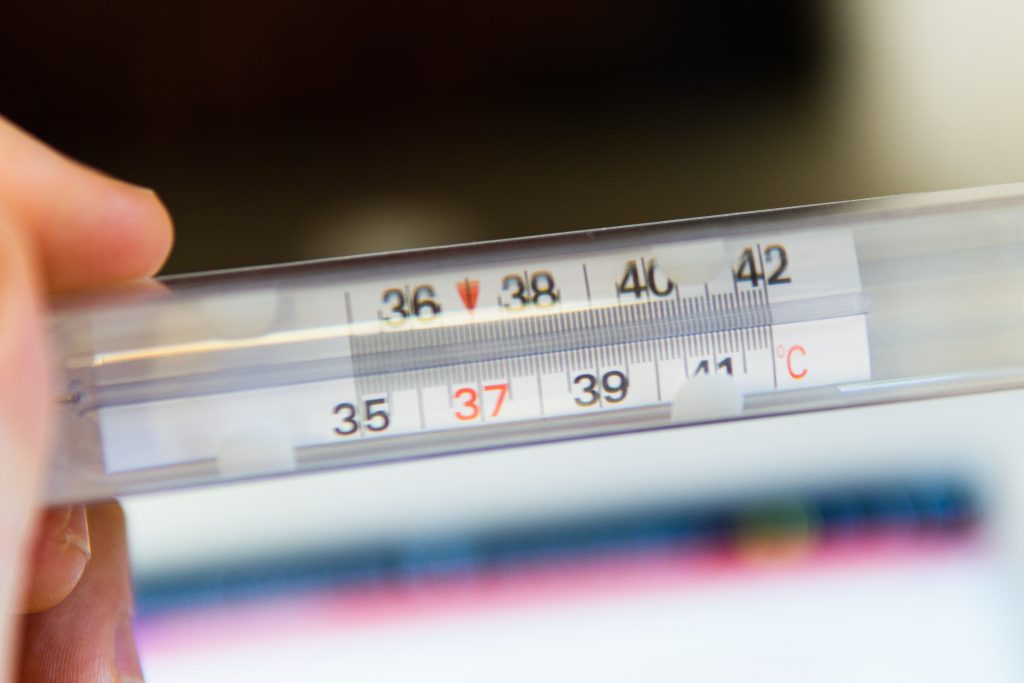
感染経路
ノロウイルスによる食中毒は、ノロウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝を生で、あるいは加熱不十分な状態で食べたり、ノロウイルスに感染した人が調理したものを食べたりするなどの原因によって起こります。
★主な感染経路
◇経口感染
ノロウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝を生で、あるいはよく加熱せずに食べた場合に起こります。
また、ノロウイルスに感染した人が調理することによって、その人の手から食べ物にノロウイルスが付着し、それを食べることなどによって二次的に感染します。
◇接触感染
感染者の糞便や嘔吐物に直接触れて手や指にノロウイルスが付着することによって感染します。
また、接触感染は、感染者が排便後に十分手を洗わずに触れたトイレのドアノブなどを介しても起こります。
◇飛沫感染
感染者の嘔吐物が床に飛散した際などに、周囲にいてノロウイルスの含まれた飛沫を吸いこむことで感染します。
◇空気感染
感染者の糞便や吐物が乾燥し、付着したほこりとともに空気中を漂います。これを吸いこんだりして、口の中へノロウイルスが侵入することで感染します。
ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイント
ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイントは、ノロウイルスを「持ち込まない」「つけない」「退治する」「拡げない」の4つです。
- 「持ち込まない」ために
ふだんから感染しないように、丁寧な手洗いや日々の健康管理を心がける。
腹痛や下痢などの症状があるときは、食品を直接取り扱う作業をしない。 - 「つけない」ために
食品や食器、調理器具などにノロウイルスを付けないように、
調理などの作業をする前などの「手洗い」をしっかりと行う。
★手を洗うタイミング
→トイレに行った後・調理施設に入る前・料理の盛り付けの前・次の調理作業に入る前など
★手の洗い方
→①手洗い前に指輪や時計を外す
②流水でよく手をぬらし、石けんをつけ、
手のひらと手の甲をよくこする
③指先・爪の間を念入りにこすり、指の間を洗う
④親指と手のひらをねじり洗う
⑤手首も忘れずに洗う
⑥洗い終わったら十分に水で流し、しっかりと水分をふき取る - 「退治する」ために
★食品に付着したノロウイルスを死滅させるために、
中心温度85℃~90℃、90秒以上の加熱を行う。
★調理器具は、洗剤などで十分に洗浄した後に、
熱湯(85℃以上)で1分以上加熱するか、
塩素消毒液(塩素濃度200ppm)に浸して消毒する。 - 「拡げない」ために
ノロウイルスが身近で発生したときには、食器や環境などの消毒を徹底すること、
また、嘔吐物などの処理の際に二次感染しないように対策をする。

これから、ノロウイルスの発生が増加する季節となります。
日ごろから予防を心がけ、この冬を元気に乗り切りましょう!!
★参考文献
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201811/3.html

